入札方式には種類がある?各方式のメリットやデメリットを徹底解説!
- 2024年11月30日
- Posted by: アールエス行政書士事務所
- Category: 入札参加資格
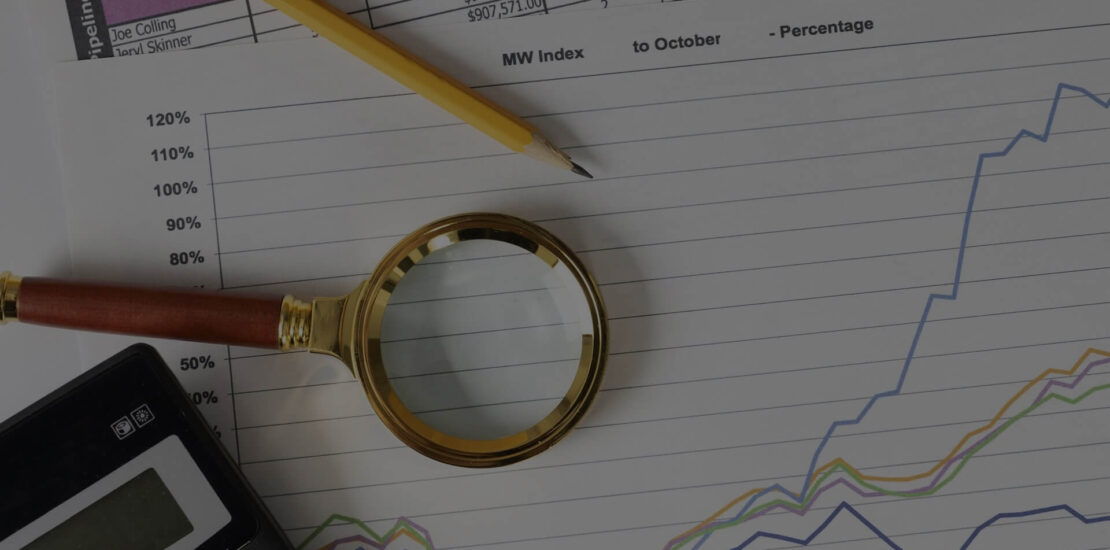
公共入札には、非常に多くの入札方式があります。
これが原因で、頭を抱えてしまっている担当者の方もたくさんいるでしょう。
そこでこの記事では、入札方式の種類や各方式の特徴について詳しく解説していきます。
入札方式の種類と特徴を理解することによって、自社に合った入札方式を見つけやすくなりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
入札とは?

入札とは、競争売買のひとつです。
具体的には、受注希望者に受注金額を提示させ、最も良い条件を提示した業者を選ぶ方式のことを指します。
以下、入札の目的と随意契約との違いについて、詳しく見ていきましょう。
目的
公共入札の目的は、公的機関と民間事業者の癒着を防ぐことです。
公的機関は、賄賂の収受や贈与が犯罪となっており、このような事態を防ぐためにキャリア層は数年ごとに人事異動が行われます。
このように、民間事業者との癒着を防ぐ仕組みが整備されており、入札はその取り組みの1つとして取り入れられています。
また、入札によって受注価格を競わせることによって、合理的な価格での受注を可能にすることも目的の1つです。
随意契約との違い
数ある入札方式の中で、例外的な方法が1つだけ存在しています。
それが、随意契約です。
随意契約とは、入札者同士で競争することなく、発注機関が任意に特定の事業者を選んで契約する方法のことです。
スピーディに受注者を選べるというメリットがありますが、その反面、受注者の恣意的な選択が行われる可能性があるといったデメリットが存在しています。
このようなトラブルを防ぎ、公平性を担保するべく、随意契約を行う場合であっても、発注機関はなるべく2社以上の事業者から見積もりを取ることとされています。
入札方式の代表的な種類

公共入札の代表的な入札方式は、大きく分けると以下3つです。
・一般競争入札
・指名競争入札
・企画競争入札(プロポーザル)
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
一般競争入札のメリット、デメリット
一般競争入札とは、国や地方公共団体が契約内容や入札参加資格を「公告」して入札を募り、最も有利な条件を提示した事業者と契約する方式のことです。
ここでいう「最も有利な条件」の判断方法には、価格の安さを重視する「価格競争方式」と、価格以外の要素も含めて総合的に評価する「総合評価落札方式」があります。
メリット
一般競争入札のメリットは、以下の通りです。
・公平性が担保されている
・実績にかかわらず入札に参加できる
・金額で落札が決まるため、ハードルが低い
数ある入札方式の中でも、総合的なメリットの多さから「一般競争入札」の案件数が最も多くなっています。
一般競争入札で実績を作り、その後、指名競争入札や企画競争入札に参加していくという方法もあります。
デメリット
一般競争入札のデメリットは、利益を確保しにくいことです。
先ほども解説したように、この方式は「価格」で落札が決まるため、安い金額を提示した事業者が有利になります。
このようなことから、利益の最大化ではなく、実績作りを目的としている場合におすすめの入札方式といえます。
指名競争入札のメリット、デメリット
指名競争入札とは、発注機関が特定の事業者を指名して、その中で入札が行われて最終的な発注先を決める方式のことです。
先ほど紹介した一般競争入札は、調達ポータルやHPで情報が公告され、不特定多数の参加者から入札を募りますが、指名競争入札は発注者から指名されないと入札に参加できません。
そんな指名競争入札は、以下の条件を満たす場合に認められます。
・入札参加者が少なく、一般競争入札の必要がない
・納品・検証・検査の難易度が極めて高い
・契約の性質や目的を鑑みて、一般競争入札が適当ではない
メリット
指名競争入札のメリットは、以下の通りです。
・落札確率が高い
・コストやスケジュールの予測が立てやすい
・中長期的な発注に期待できる
指名競争入札は、そもそも参加する事業者の数が少ないため、落札確率が高くなります。
また、価格勝負になる一般競争入札に比べると、コストやスケジュールの予測が立てやすいことも、この方式ならではのメリットといえるでしょう。
さらに、受注できた場合は継続的な発注を受けられる可能性があるため、利益を最大化しやすくなります。
デメリット
指名競争入札のデメリットは、以下の通りです。
・指名がなければ入札に参加できない
・新規参入の事業者にとってはハードルが高い
一般競争入札の場合、入札参加資格を取得すれば基本的に誰でも入札に参加できます。
一方、指名競争入札の場合は「指名」がなければ土俵にすら上がれません。
また、過去に指名実績がある事業者を中心に選ばれる傾向にあるため、新規参入の事業者にとっては若干ハードルが高くなります。
企画競争入札のメリット、デメリット
企画競争入札は、入札価格だけでなく、
・企画提案
・技術提案
などを総合的に考慮して受注者を決める方式で、別名「プロポーザル方式」とも呼ばれています。
該当テーマに基づく企画書などを提出し、最適な提案をした事業者と契約するというのが、企画競争入札の特徴です。
企画書の提出については、公募に基づいて行われる場合もあれば、指名に基づいて行われる場合もあります。
メリット
企画競争入札のメリットは、以下の通りです。
・利益を確保しやすい
・評価基準が明確である
企画競争入札は、企画内容で評価されるため、価格を評価される一般競争入札に比べると利益を確保しやすくなります。
また、明確な審査項目が公表されているケースが多いため、項目に合わせて企画書を作成できるというメリットもあります。
デメリット
企画競争入札のデメリットは、以下の通りです。
・ある程度の実績がないと落札が難しくなる
・提案内容の作成に工数がかかる
先ほども解説したように、企画競争入札では明確な評価基準が公開されることが多いですが、その中に「落札実績」が盛り込まれることも珍しくありません。
つまり、過去に類似案件で落札した実績がない場合、落札確率が下がるということです。
もちろん、落札実績がないからといって絶対に通らないというわけではありませんが、実績がある事業者に比べると不利になります。
また、提案準備に工数がかかることも企画競争入札ならではのデメリットといえるでしょう。
入札の流れ・参加方法

では次に、入札の流れや参加方法について詳しく解説していきます。
ステップ1:入札参加資格を取得する
入札に参加するためには、発注機関が定める「入札参加資格」を取得しなければなりません。
一般競争入札は、基本的に誰でも参加できるものですが、これはあくまでも「入札参加資格を取得している者」に限られます。
入札参加資格は、案件を探してから取得するケースもありますが、スムーズに参加するためにも、関連する資格をあらかじめ取得しておくのがおすすめです。
ただし、資格の取得には申請が必要であり、用意すべき書類も多岐に渡ります。
なおかつ、申請には期限がありますので、時間に余裕を持って進めることが大切です。
スムーズかつ正確に申請を進めていきたい場合は、行政書士に依頼するのがおすすめです。
(参考:入札参加資格とは一体何?種類や等級、申請の流れを徹底解説!)
ステップ2:案件を探す
入札参加資格の取得が終わったら、案件を探していきます。
案件は、以下のようなサイト・媒体で探せます。
・官報
・自治体や関係機関のWebサイト
・業界紙(専門誌)
・入札情報サービス
これらのサイト・媒体を日ごろからチェックしたり、アラート機能を活用したりして自社にピッタリの案件を見つけましょう。
案件のピックアップが終わったら、
・案件名
・発注者
・予定価格
・入札日程
などを整理しつつ、自社の強みを活かせる案件を選別していきます。
ステップ3:入札の準備を行う
入札したい案件が決まったら、入札準備を行いましょう。
具体的には、以下のような準備が必要になります。
・仕様書の取得
・入札説明会への参加
・入札書類の作成
仕様書には、入札方式や要件などの詳細情報が掲載されています。
Webサイトからダウンロードできる場合もあれば、関係機関に資料請求して取り寄せる場合もありますので、事前に確認しておいてください。
発注機関によっては、入札説明会への参加が「必須要件」になっていることがあります。
この場合は、事前に入札説明会に参加しなければなりません。
また、仕様書が入札説明会で手渡されるケースもありますので、こちらも要チェックです。
入札書類については、仕様書に記載されているルールや条件に従って作成していきます。
ステップ4:入札~契約
入札準備が終わったら、いよいよ入札です。
入札方法は発注機関によって異なりますが、以下3つの方法が用いられることが多くなっています。
・会場入札
・電子入札
・郵送入札
入札については、期間中に1回しか行えません。
そのため、競合他社がどれくらいの価格を出してくるのかを予測しつつ、慎重に検討していくことが大切です。
入札後、無事に落札できたら発注機関と契約を締結します。
その後のトラブルを防ぐためにも、契約書の内容を十分にチェックした上で、所定の手続きを済ませましょう。
入札参加資格の取得申請は「アールエス行政書士事務所」にお任せください!
入札に参加するためには、入札参加資格が必要です。
難しい条件は設けられていないものの、申請には様々な書類が必要であり、不備があると申請が通りません。
また、申請には期限が設けられているケースが大半ですので、時間に余裕をもって進める必要があります。
とはいえ、中には「時間が無くて申請準備ができない」と悩んでいる方もいるでしょう。
そのような方は、物品・役務・委託の入札参加資格申請代行を行っている「アールエス行政書士事務所」にご相談ください。
当事務所では、オンラインサポートを行っているため、全国どこからでもご利用いただけます。
また、電子入札で必要になる「電子証明書」の取得支援も行っていますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
まとめ
公共入札には、様々な入札方式があります。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、各方式の特徴を理解した上で、自社に合った入札方式を考えていくことが大切です。
また、入札に参加するためには「入札参加資格」が必要であり、この資格がないと土俵に上がることすらできません。
ただ、入札参加資格の取得には様々な準備が必要であり、時間がかかってしまうこともあります。
スムーズに入札参加資格を取得したい方は、アールエス行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
入札参加資格の申請には、必要な書類の準備や記入、注意事項、期限など気をつけなければいけないことが多くあります。申請手続きに慣れていないと、通常業務と並行して行うのは大変です。
「業務に影響を出したくない」と入札参加資格の取得に躊躇している方は、下記フォームよりアールエス行政書士事務所に一度ご相談ください。
お急ぎの場合は070-1326-1494までお電話ください。
または下記QRコードよりLINEにてお問い合わせください。
